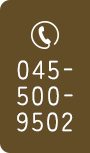百日咳について
2025年8月現在も流行がつづく百日咳について解説します。
<百日咳とは?>
百日咳菌という細菌が原因で起こる、激しい咳を特徴とする呼吸器感染症です。
咳がよくなるまでに約100日間と長く時間がかかるため百日咳と呼ばれています。感染者の咳やくしゃみによって飛び散ったしぶきを吸い込んでしまうことや(飛沫感染)、百日咳菌が付着した身の回りの物品などを手で触ること(接触感染)により感染し発症します。
子供に多い病気ですが、大人でも感染します。大人の場合、咳が1~2か月続くだけで発作的な症状が出ないこともあるため、ただの風邪として放置されることが少なくありません。
<症状の経過は?>
以下のように分けられます。
●カタル期(約2週間)
鼻汁、くしゃみ、軽い咳などで始まり、徐々に咳の回数が増えていきます。熱はあっても微熱程度であることが多いです。
風邪と症状がほとんど変わらないため診断が難しい一方で、後述のようにこのタイミングで治療を開始しなければ治療効果は期待できません。
また、最も感染力の強い時期でもあり、知らないうちに周囲に感染を広げてしまっている場合があります。
●痙咳期(約2~3週間)
次第に百日咳に特徴的な発作性けいれん性の咳になります。
この時期の咳は、百日咳菌そのもの、百日咳菌が産生した毒素による影響で気道が過敏になっていることが原因です。咳の勢いで嘔吐することもあります。
6か月未満の乳児は重症化のリスクが高く、呼吸困難や無呼吸、肺炎や脳症の合併の可能性があり、注意が必要です。
●回復期(2~3週間)
発作性の咳は徐々に回復に向かいます。
<診断方法>
インフルエンザやコロナのように、その場で結果が分かる、高精度の検査が存在しないため、診断が難しいのが現状です。百日咳の検査には以下のような種類があります。
① PCR検査
鼻咽頭ぬぐい液を採取して、百日咳菌の遺伝子を増幅、検出します。
メリット:診断の精度が高い。
デメリット:結果が判明するまで数日かかってしまう。
※PCR検査をその場で行うことのできる検査機器が存在しますが、ほとんどの医療機関で設置されていないのが現状です。当院でも即日対応はできず、結果判明に数日を要しています。
② 抗体検査
血液検査を行い、百日咳菌に対するIgG抗体を測定します。抗体が100EU/ml以上あれば確定診断となります。
メリット:採血のため検査が比較的簡単に行える。
デメリット:結果が判明するまで数日〜1週間程度かかってしまう。発症から4週間以上経過しないと数値が上がらない可能性がある。中途半端に数値が上昇している場合、解釈が難しい(1回目の採血から2週間以上空けて再度抗体検査を行い(ペア血清)、判断することがあります)。
③ 抗原定性検査
鼻咽頭ぬぐい液を採取して、専用のキットを用いて15分ほどで結果が判明します。
メリット:簡単に早く検査ができる。
デメリット:診断精度がとても低い。
④ 培養検査
鼻咽頭ぬぐい液を用いて、百日咳菌の培養を行います。培養で菌が生えてくれば確定診断となります。ただし、1週間以上時間がかかること、偽陰性(本当は百日咳菌がいるにも関わらず、検出できないこと)が多いことから、あまり実施されていません。
<治療>
マクロライド系の抗生物質の内服を行います。
治療は、発症から2~3週間以内のカタル期に行うのが効果的とされており、痙咳期に治療を開始しても効果は限定的です。
その一方で、百日咳のカタル期は通常の風邪と見分けがつかないこと、迅速で精度の高い検査がないことから、カタル期に治療開始することは難しいのが現状です。
痙咳期への対応は、基本的に咳止めや気管支を拡げる薬を用いながら、症状が改善するのを待ちます。この時期の抗生剤治療は、症状を改善させることは期待できないものの、周囲への感染を防ぐという目的では意義があると考えられています。
<予防>
ワクチン接種によって予防をすることができます。
日本では小児期に定期接種として百日咳のワクチンを接種していますが、時間とともに効果も減弱します。大人になって百日咳に感染してしまうのは、ワクチン接種から時間が経過し免疫が落ちているためです。小さな子供や高齢者、妊婦など、周囲に重症化リスクが高い家族がいる方は、ワクチンの再接種を検討されてはいかがでしょうか。